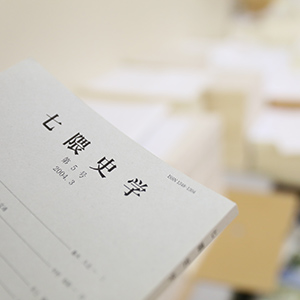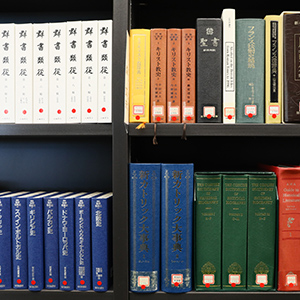史学専攻の特色
本専攻は、日本史・東洋史・西洋史・考古学の4専修に分かれ、それぞれに演習・特講・史料 講読(前期)、特研・特論(後期)が開講されています。
専任教員は、日本史では「政治・経済・文化各面からみた中世史・近世史」や「幕末維新期の政治・経済史」、「昭和戦中・戦後期の社会」、東洋史では「唐宋時代史」や「明清社会経済史」、西洋史では「アメリカ史」や「中近世ヨーロッパ史」、考古学では「新石器時代~中近世」や「東アジア考古学」、「貨幣史」などについて研究しています。
そのほか、各専修共に古代から現代に至るまでの各分野について、非常勤の専門家による授業も開講しています。
カリキュラム
博士課程前期
閲覧したい分野のタブをクリックしてください。
- 日本史専修
- 西洋史専修
- 東洋史専修
- 考古学専修
| 部門 | 授業科目 | 単位数 |
|---|---|---|
| 日本史専修 | 日本史演習 | 4又は8 |
| 日本史特講Ⅰa | 2 | |
| 日本史特講Ⅰb | 2 | |
| 日本史特講Ⅰc | 2 | |
| 日本史特講Ⅰd | 2 | |
| 日本史特講Ⅱa | 2 | |
| 日本史特講Ⅱb | 2 | |
| 日本史特講Ⅱc | 2 | |
| 日本史特講Ⅱd | 2 | |
| 日本史特講Ⅲa | 2 | |
| 日本史特講Ⅲb | 2 | |
| 日本史特講Ⅲc | 2 | |
| 日本史特講Ⅲd | 2 | |
| 日本史特講Ⅳa | 2 | |
| 日本史特講Ⅳb | 2 | |
| 日本史特講Ⅳc | 2 | |
| 日本史特講Ⅳd | 2 | |
| 日本史特講Ⅴa | 2 | |
| 日本史特講Ⅴb | 2 | |
| 日本史特講Ⅴc | 2 | |
| 日本史特講Ⅴd | 2 | |
| 日本史特講Ⅵa | 2 | |
| 日本史特講Ⅵb | 2 | |
| 日本史特講Ⅵc | 2 | |
| 日本史特講Ⅵd | 2 | |
| 日本史史料講読A | 4 | |
| 日本史史料講読B | 4 |
| 部門 | 授業科目 | 単位数 |
|---|---|---|
| 西洋史専修 | 西洋史演習 | 4又は8 |
| 西洋史特講Ⅰa | 2 | |
| 西洋史特講Ⅰb | 2 | |
| 西洋史特講Ⅰc | 2 | |
| 西洋史特講Ⅰd | 2 | |
| 西洋史特講Ⅱa | 2 | |
| 西洋史特講Ⅱb | 2 | |
| 西洋史特講Ⅱc | 2 | |
| 西洋史特講Ⅱd | 2 | |
| 西洋史特講Ⅲa | 2 | |
| 西洋史特講Ⅲb | 2 | |
| 西洋史特講Ⅲc | 2 | |
| 西洋史特講Ⅲd | 2 | |
| 西洋史特講Ⅳa | 2 | |
| 西洋史特講Ⅳb | 2 | |
| 西洋史特講Ⅳc | 2 | |
| 西洋史特講Ⅳd | 2 | |
| 西洋史特講Ⅴa | 2 | |
| 西洋史特講Ⅴb | 2 | |
| 西洋史特講Ⅴc | 2 | |
| 西洋史特講Ⅴd | 2 | |
| 西洋史史料講読A | 4 | |
| 西洋史史料講読B | 4 |
| 部門 | 授業科目 | 単位数 |
|---|---|---|
| 東洋史専修 | 東洋史演習 | 4又は8 |
| 東洋史特講Ⅰa | 2 | |
| 東洋史特講Ⅰb | 2 | |
| 東洋史特講Ⅰc | 2 | |
| 東洋史特講Ⅰd | 2 | |
| 東洋史特講Ⅱa | 2 | |
| 東洋史特講Ⅱb | 2 | |
| 東洋史特講Ⅱc | 2 | |
| 東洋史特講Ⅱd | 2 | |
| 東洋史特講Ⅲa | 2 | |
| 東洋史特講Ⅲb | 2 | |
| 東洋史特講Ⅲc | 2 | |
| 東洋史特講Ⅲd | 2 | |
| 東洋史史料講読A | 4 | |
| 東洋史史料講読B | 4 |
| 部門 | 授業科目 | 単位数 |
|---|---|---|
| 考古学専修 | 考古学演習 | 4又は8 |
| 考古学特講Ⅰa | 2 | |
| 考古学特講Ⅰb | 2 | |
| 考古学特講Ⅰc | 2 | |
| 考古学特講Ⅰd | 2 | |
| 考古学特講Ⅱa | 2 | |
| 考古学特講Ⅱb | 2 | |
| 考古学特講Ⅱc | 2 | |
| 考古学特講Ⅱd | 2 | |
| 考古学特講Ⅲa | 2 | |
| 考古学特講Ⅲb | 2 | |
| 考古学特講Ⅲc | 2 | |
| 考古学特講Ⅲd | 2 | |
| 考古学特講Ⅳa | 2 | |
| 考古学特講Ⅳb | 2 | |
| 考古学特講Ⅳc | 2 | |
| 考古学特講Ⅳd | 2 | |
| 考古学方法論A | 4 | |
| 考古学方法論B | 4 |
博士課程後期
閲覧したい分野のタブをクリックしてください。
- 日本史専修
- 西洋史専修
- 東洋史専修
- 考古学専修
| 部門 | 授業科目 | 単位数 |
|---|---|---|
| 日本史専修 | 日本史学特別研究Ⅰ | 12 |
| 日本史学特別研究Ⅱ | 12 | |
| 日本史学特別研究Ⅲ | 12 | |
| 日本史学特論Ⅰ | 4 | |
| 日本史学特論Ⅱ | 4 | |
| 日本史学特論Ⅲ | 4 |
| 部門 | 授業科目 | 単位数 |
|---|---|---|
| 西洋史専修 | 西洋史学特別研究Ⅰ | 12 |
| 西洋史学特別研究Ⅱ | 12 | |
| 西洋史学特論Ⅰ | 4 | |
| 西洋史学特論Ⅱ | 4 |
| 部門 | 授業科目 | 単位数 |
|---|---|---|
| 東洋史専修 | 東洋史学特別研究Ⅰ | 12 |
| 東洋史学特別研究Ⅱ | 12 | |
| 東洋史学特論Ⅰ | 4 | |
| 東洋史学特論Ⅱ | 4 |
| 部門 | 授業科目 | 単位数 |
|---|---|---|
| 考古学専修 | 考古学特別研究Ⅰ | 12 |
| 考古学特別研究Ⅱ | 12 | |
| 考古学特論Ⅰ | 4 | |
| 考古学特論Ⅱ | 4 |
修士・博士の学位取得プロセス
博士課程前期
修士学位申請のための要件
- 在籍期間
修士課程又は博士課程前期に2年以上在学した者でなければならない。 - 単位要件
所定の授業科目について合計32単位以上を修得しなければならない。
学位申請までのプロセス
- 研究指導体制等
入学時において決定した指導教員から、研究テーマの設定、研究計画の作成など専門分野に関する指導を受ける。大学院学生は一連の研究活動を行い、研究報告会や学会などでの成果発表を通じて専門家としての素養を身につける。 -
1年次において
4月 : 専攻全体および専修単位で行われるオリエンテーションに出席。指導教員から論文作成に関する指導を受けながら、「研究計画書」を作成する。
5月~翌年3月 : 指導教員が担当する「演習」において中間報告を行い、研究の進捗状況を報告する。教員や大学院生から指導・助言を受け、研究を進めていく上での問題点を明らかにするとともに、その解決方法について検討する。また、各専修の判断により、適宜、中間報告会を行い、研究の進捗状況を報告し、指導教員や他の教員および大学院生から広く指導・助言を受ける。 -
2年次において
4月 : 1年次の総括を踏まえ、必要に応じて研究計画の見直しを行う。
4月~翌年1月 : 継続して「演習」などで研究成果を報告し、研究成果をまとめてゆくプロセスを学ぶ。一定レベル以上の研究成果が得られた場合には学会発表や論文投稿を行い、広く内外の評価を受ける。
10月 ~翌年1月: 修士論文の論題を提出し、その後決定する主査・副査の指導を受ける。
1月~2月 : 修士論文を提出する。修士論文の口頭試問(最終試験)を行い、主査・副査からの質疑に答える。修士論文発表会で研究成果を発表し、教員や学生からの質疑に答える。
博士課程後期
博士学位申請のための要件
- 在籍期間
博士課程後期に3年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた者。
学位申請までのプロセス
- 研究指導体制
入学時において決定した指導教員から、専門分野の研究活動に関する指導を受ける。大学院学生は一連の研究活動を行い、その成果を学会で報告するとともに、専門の学術誌に論文を投稿して厳正な査読審査を経験することにより、自立して研究活動を遂行し得る能力を身につける。 -
1年次において
4月:研究計画について指導教員と相談を重ね、博士論文の準備についての骨格をかためる。
5月~翌年3月:指導教員との綿密な議論のもとに研究成果を蓄積していく。指導教員が担当する「特別研究」において研究の進捗状況を報告する。指導教員から評価や助言・指導を受け、研究を進めていく上での問題点を明らかにするとともに、その解決方法について検討する。まとまった成果が得られたところで、学会等で積極的に発表し、広く内外の評価を受ける。 -
2年次において
4月:1年次の研究経過を踏まえ、必要に応じて研究計画の見直しを行う。
4月~翌年3月:学位論文の提出に向け、継続して「特別研究」において研究の進捗状況を確認し、指導教員との綿密な議論を研究内容にフィードバックしていく。引き続き学会等で研究成果を積極的に発表し、広く内外の評価を受けるとともに、専門の学術誌に論文投稿を行い、査読審査を経験する。 -
3年次において
4月~10月:研究を進めるなかで引き続き学会や専門の学術誌に研究成果を発表し、広く内外の評価を受ける。これまでの研究業績および成果をまとめ、学位論文を作成する。指導教員の承認を経て、学位論文を提出し、学位審査請求を行う。学位論文の作成に際しては、指導教員から内容および構成に関して具体的な指導を受ける。
11月~1月:博士学位申請論文の発表会(公聴会)(最終試験)を行う。研究成果を総括し、主査・副査および出席者からの質疑に答える。