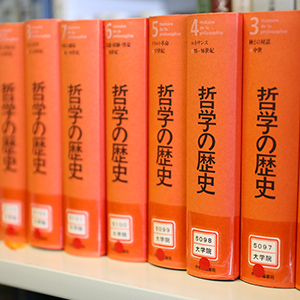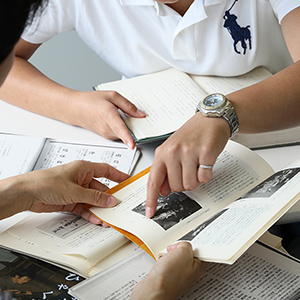社会・文化論専攻の特色
「人間社会」分野では社会システム論(社会学)に関する演習と特講が、「人間文化」分野 では文化構造論(文化人類学・民俗学)、思想文化論(哲学・宗教学)、表象文化論(芸術学・美術史)に関する演習と特講が中核になります。各専修に共通する社会・文化に関する基礎論は必修とされています。国内および国外の社会調査やフィールドワークに秀でた専門家、現場に通暁する博物館学芸員やジャーナリストを養成します。
カリキュラム
修士課程
必修科目
| 授業科目 | 単位数 |
|---|---|
| 社会・文化基礎論Ⅰ | 2 |
| 社会・文化基礎論Ⅱ | 2 |
| 社会・文化基礎論Ⅲ | 2 |
| 社会・文化基礎論Ⅳ | 2 |
選択必修科目
| 分野 | 授業科目 | 単位数 |
|---|---|---|
| 人間社会 | 社会システム論演習Ⅰ | 8 |
| 社会システム論演習Ⅱ | 8 | |
| 社会システム論特講Ⅰ | 4 | |
| 社会システム論特講Ⅱ | 4 | |
| 人間文化 | 文化構造論演習Ⅰ | 8 |
| 文化構造論演習Ⅱ | 8 | |
| 文化構造論演習Ⅲ | 8 | |
| 文化構造論特講Ⅰ | 4 | |
| 文化構造論特講Ⅱ | 4 | |
| 文化構造論特講Ⅲ | 4 | |
| 思想文化論演習Ⅰ | 8 | |
| 思想文化論演習Ⅱ | 8 | |
| 思想文化論演習Ⅲ | 8 | |
| 思想文化論特講Ⅰ | 4 | |
| 思想文化論特講Ⅱ | 4 | |
| 思想文化論特講Ⅲ | 4 | |
| 表象文化論演習Ⅰ | 8 | |
| 表象文化論演習Ⅱ | 8 | |
| 表象文化論演習Ⅲ | 8 | |
| 表象文化論特講Ⅰ | 4 | |
| 表象文化論特講Ⅱ | 4 | |
| 表象文化論特講Ⅲ | 4 | |
選択科目
| 授業科目 | 単位数 |
|---|---|
| 社会システム論文献講読Ⅰ | 2 |
| 社会システム論文献講読Ⅱ | 2 |
| 文化構造論文献講読Ⅰ | 2 |
| 文化構造論文献講読Ⅱ | 2 |
| 思想文化論文献講読Ⅰ | 2 |
| 思想文化論文献講読Ⅱ | 2 |
| 表象文化論文献講読Ⅰ | 2 |
| 表象文化論文献講読Ⅱ | 2 |
| 表象文化論文献講読Ⅲ | 2 |
| 現代社会論 | 2 |
| 比較社会文化論 | 2 |
| 文化心理学 | 2 |
| 人間性心理学 | 2 |
| 応用倫理学 | 2 |
| 言語文化論 | 2 |
| 文化価値論 | 2 |
修士・博士の学位取得プロセス
修士学位申請のための要件
- 在籍期間
修士課程又は博士課程前期に2年以上在学した者でなければならない。 - 単位要件
所定の授業科目について合計32単位以上を修得しなければならない。
学位申請までのプロセス
- 研究指導体制
専攻所属の大学院生は、入学時において決定した指導教員および専門分野の複数の教員から、研究テーマの設定、研究計画の作成など学位論文(修士論文)に関する指導を受ける。専攻所属の大学院生は一連の研究活動を行い、「研究テーマ」「論文構成」「論文内容」の発表を通じて、専門家としての知識を身につけ、学位論文(修士論文)を提出し修士学位の申請を行う。 -
1年次において
4月: 「研究計画書」を提出する。
6月: 「修士論文検討会」 1回目:研究テーマを発表する。
11月:「修士論文検討会」 2回目:論文構成を発表する。 -
2年次において
6月: 「修士論文検討会」 3回目:論文内容を発表する。
10月:「修士論文論題」を提出する。
10月: 通常委員会にて承認された副査からも指導を受ける。
11月:「修士論文検討会」 4回目:論文内容を発表する。
1月: 修士論文を提出し、修士論文発表会で発表を行う。
2月: 口頭試問(最終試験)を受ける。
以上、計 4回の修士論文検討会と修士論文発表会は、すべて公開とする。