2025.04.28
私たちの最近の研究について 佐藤仁、伊藤亜希子:教育・臨床心理専攻
アメリカの教師教育を専門とする佐藤とドイツの異文化間教育を専門とする伊藤で、2018年より共同研究を行っています。「多文化共生に向けた教員養成教育の実践的研究―アメリカとドイツに着目して―」(2018・2019年度福岡大学推奨研究プロジェクト)の研究成果をもとに、2022年度より科研費基盤研究(B)「多様性を志向する教師教育の国際比較研究」(研究代表者:佐藤仁)に取り組んでおり、2025年度が最終年度となります。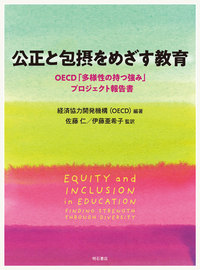
教育現場では、多様なニーズのある子どもたちの包摂は課題の一つとなっています。日本で言えば、例えば日本語指導が必要な子どもたち、障害のある子どもたち、LGBTQ+の子どもたち、特異な才能のある子どもたちが学校で学んでいます。多様な子どもたちのニーズを踏まえ、どのように公正で包摂的な教育を実現することができるでしょうか。日本ではこうした多様性に対応できる教師教育について、まだ十分に議論されていません。
私たちの比較研究では、アメリカ、イギリス、オーストラリア、韓国、スウェーデン、ドイツ、ニュージーランド、フランスの8か国の教師教育を専門とする研究者が集まり、各国の文脈を踏まえた「多様性を志向する教師教育」の実態を研究・政策・実践の観点から分析し、その特徴を解明することを目指しています。
これまでの成果としては、経済協力開発機構(OECD)が2023年に発表した報告書Equity and Inclusion in Education: Finding Strength through Diversityを翻訳し、2024年6月に出版しました。同書では、教育における多様性や包摂・公正の概念が整理され、世界各国の実践や政策が紹介されています。翻訳に際しては、2023年10月末にパリにあるOECDを訪問し、報告書のプロジェクトリーダーDr. Lucie Cerna氏と有意義な意見交換を行いました。
また、2024年9月にはドイツ・ブレーメン大学のProf. Dr. phil. Yasemin Karakasoglu氏をお招きし、国際セミナーを本学で開催しました。セミナーでは、ブレーメン大学の教員養成における「学校における異質性への対応」モジュールについてお話しいただき、参加者とともに充実した議論を行うことができました。これを機に、2025年5月にブレーメン大学で開催されるInternational Teaching Weekのオープニングの基調講演として、佐藤・伊藤が本共同研究の成果を報告する機会をいただき、国際的な研究交流も活発に進めています。

世界的に、多様性の尊重や包摂へのバックラッシュが起きている今だからこそ、国際比較から多様性を志向する教師教育の意義を発信することには大きな意味があります。本共同研究の最終成果は、多くの人に手に取ってもらえるよう書籍化する予定です。
参考:経済協力開発機構(OECD)編著、佐藤仁・伊藤亜希子監訳(2024)『公正と包摂をめざす教育―OECD「多様性の持つ強み」プロジェクト報告書―』明石書店
